(サムネイル:Image by Gerd Altmann from Pixabay)
こんばんは。
ピクセルアニメクリエイターのおかか容疑者でございます。
Amazonセールで買ってみた本、以前の「文章力が、最強の武器である。」もわかりやすくて非常によい本でしたが、他の本も大当たりでございました。
「文章力が、最強の武器である。」は文章を書くこと全般のお話でしたので、日常生活全てにおいて役立つ本でした。
対して今回ご紹介する本はだいぶガチなビジネス書という感じでございますね。
というわけで本日は「替えがきかない人材になるための専門性の身につけ方」(国分峰樹)より、考えさせられた一節をご紹介いたします。
著者の国分さんは電通のトランスフォーメーション・プロデュース部長とのことです。
非常に偏見ながら、「電通」というといかにも古くからの運営を続けている大企業、というイメージをワタシは持ってしまいます。
しかしこの本を読むと、「電通の中にはこんな先鋭的な思考をなされている方がおられるんだ。これは相当、電通の内部は今のワタシのイメージとは違うんだろうな」、という感想を抱かざるを得ません。
それくらいに衝撃の大きい一冊でございました。
この本は「専門性」について語られております。
専門性、と聞くと「一般人がよく知らない専門知識をいっぱい知っている」というイメージがございます。
しかしそれだけの「専門知識をインプットするだけ」では不十分であると。これからの世界で本当に必要となるのは「専門知識のアウトプット」。すなわち「新しい知識を創り出すこと」であると著者は指摘します。
序盤でこういった読者の意識改革を促し、中盤からどのようなプロセスを経て自分の「専門性」を創っていくか。といった流れになっております。
そんなわけで特に序盤はだいぶ刺してきますね。「人生戦略マニュアル」と同じくらいのレベルで刺してきます。
自分ごとでもありながらかなり痛快ですので、そのあたりもいい意味でショックを受けながら読んでいただけるとよいかなと。
グローバル化、AIの登場により、これからビジネスパーソンは何を目指していけばいいのか?
という悩みを持つ方には本当にオススメします。
というわけで今回はこの「専門性」についてのお話でございます。
著者はこの本の中で「小さな問いを立てる」ことの重要性を説いております。(問いの立て方のヒントもいろいろ書いておられますが、その辺りは本書をお読みください。)
この「小さな問い」をもう少し具体的におもしろく表現した部分がございましたので引用いたしますね。
この専門領域の土地勘というのは、とてもわかりやすい比喩表現で、たとえばカリフォルニア州に精通した人になろうと思ったときに、添乗員さんに引率してもらって観光スポットを回ったとしても、現地の土地勘は養われません。土地勘を養うためには、ガイドブックを片手に自分でいろいろと見て回る必要があります。
「替えがきかない人材になるための専門性の身につけ方」(国分峰樹)
すると、最初はカリフォルニア州をマスターしようと思っていたとしても、それでは範囲があまりに広すぎることがわかってきて、ロサンゼルスにするかサンフランシスコにするか、はたまたサンディエゴなのかサクラメントなのか、自分が掘り下げたい領域を絞っていくことになります。
ロサンゼルスに着目したとして、ロサンゼルスのお店をすべて見て回るのはこれまた長い道のりになりますので、エリアを絞るのかジャンルを絞るのかといったピンを立てていくことが必要です。
そこで、ロサンゼルスのLGBTカルチャーを入口にして、そのエリアを深掘りしていきたいと目印をつけるのが、問いを立てるのに近いイメージといえます。
実際の土地で問いの立て方を例えるとこうなるわけですな。
地球全体から見たら、「カリフォルニア州」というアメリカの一つの州ってかなり絞った選択肢なんですよね。
しかしそれでもまだ広すぎると。
本当に小さな問いということであれば、その中の一つの町、さらにその中の特定の文化、といった部分まで絞り込む。
ここで例に出している「ロサンゼルスでのLGBT文化」という分野だけでも相当調べられることがあるはずですよね。まずはこのレベルから達成できなくては、より大きなことなど調べられるはずもない。
何かを調べるにはとにかく入り口を狭く、小さくすること。これが重要なポイントであると述べておられます。
「問いを立てる」ことに関してもう一つ、著者がドラッカーとアインシュタインの言葉を引用して、その重要性を強調している一節もございました。
併せてご紹介しておきましょう。
世界的な経営学者であるピーター・ドラッカーさんは、今から五〇年以上前に〈いちばん重要で、なおかつむずかしいのは、正しい答えを見つけることではない。正しい問いを見つけることだ。誤った問いへの正しい答えほど、むだなものはない〉という言葉を残しました。
「替えがきかない人材になるための専門性の身につけ方」(国分峰樹)
さらに、かつてアインシュタインは、〈もし問題を解決する時間が一時間あり、自分の人生がその問題の解決にかかっているなら、わたしは適切な問いを導き出すことに最初の五五分間を費やすでしょう。適切な問いがわかれば、問題は五分で解けるからです〉と語ったという逸話もあります。
このお二人の言葉からも、正しい問いを立てるのがいかに難しく、また大切なことなのかがうかがえますね。
アインシュタインの言葉については、現代だとAIが発展してきているところがあり、こちらが問題さえ提起すれば(正しいかはともかく)AIが解決にかなり貢献してくれる。という時代になりつつあります。
これを踏まえるとすごくリアルな話だなぁと。
ドラッカーの「誤った問いへの正しい答えほど、むだなものはない」に関しては「人生戦略マニュアル」でも印象深い話が語られていたんですよね。
精神病院に入っていた一見まともな紳士に見える人が、著者と二人で晴れた日に外にいたときに突如隠れ出した。
どうしたのかと訪ねると「敵に狙われている」と。
その人は太陽の熱を熱線銃の攻撃と勘違いしていた、というオチなのですが。
確かに、本当に敵に命を狙われているのなら、この人が取った行動はかなり適切だったと言えるでしょう。しかし行動の根本の時点で間違っていたため、ただの滑稽な行動となってしまった。
笑い話のようなものですが、実際にこのような行動が取られる場面というのは、実生活でもあるのではないかなと思ってしまいますね。
「問いを立てる」ことについてはもっと知っておく必要があるな、と感じておりますので、もう少し関連した本を探してみたいなと思います。今までの時代でも重要なスキルだったとは思いますが、時代の変化によってより重要度が増しているのだなと。や、学びたいことが多いですね。おもしろい。
さて…そろそろお時間です。
またのご面会、心よりお待ちしております。
この記事がお気に召したなら、
◎ギャラリーからワタシの作品を見ていただいたり、
☆Misskeyアカウント(@daidaimyou)
☆Caraアカウント
☆X(旧Twitter)アカウント(低浮上)(@daidaimyou)
をフォローいただけますと脱獄の励みになります。よろしくお願いいたします。
ドット絵(一枚絵・アニメーション)制作のお仕事も承っております。
お仕事依頼ページよりご連絡くださいませ。(現在受付停止中)
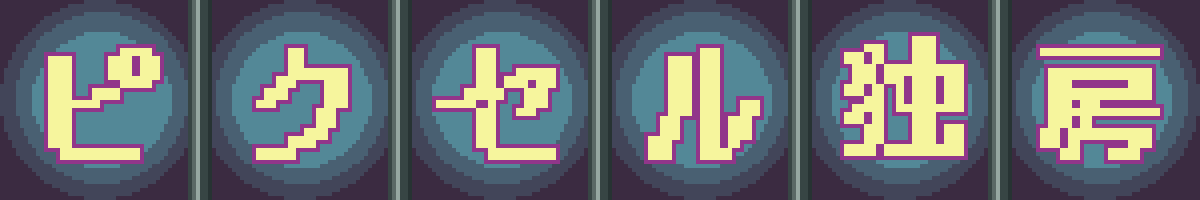



コメント